専修学校・学科紹介
商業実務専門課程 食品工学科
【 食品を創るということは 「 人 」 そのものを創るということ 】
食品工学(しょくひんこうがく、英語:food engineering)とは、食品製造業において食品の加工・保存・安全性を効率的に行うことを目的とした連続HACCPチェーンを応用した一分野です。
当学校では、素材管理→加工→製造→流通→販売まで、食品になるまでの知識、実技、職場体験を通じ、工学的な効率化、人的作業に関するマネジメントの必要性など食品専門職業に関する人材育成が目標です。
すべての食品関連事業に対して、対応可能な製造環境や危害要因分析重要管理点、生物学的危害要因(細菌・ウィルスなど)、科学的要因 (農薬・アレルギー物質など)、物理的要因 (使用機器など)があり、摂取することで健康被害を生じる可能性のあるもの) について、食品取り扱いの教育・実技などを含め、国際的に導入されているHACCP (原材料の入荷状態から製造→出荷までの危害要因を排除・未然に防ぐ) に関するオペレーションシステムを通じ、加工流通、販売まで6次産業化を連携させる連続HACCPに対する意識向上を目指し、2年間を通して理論・実技を学びます。
特に素材である「手入れする農業」「手入れする漁業」は食品工学において注目されている点です。
6次産業の食品原料を基礎とした考え方に基づいて講義、実技内容が多岐にわたり体系化されます。
食品工学科を構成している各種単位操作について、 講述し,問題や課題を工学的アプローチで解決しようとするのが理論であり、その基本的な内容について学習することで、食品安全工学の基礎能力を身につけ、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的としています。
機械化がすすまない分野で食品工学的に効率化を求めるためには、漁業権をもった漁師や農家が魚や野菜を市場で売る時代は終わり、生産者自身が加工品の製造・販売を行い、生産・ 加工・流通を一体化させることによる付加価値の拡大へと時代は流れようとしております(開発型)
そして生産者(漁業者・農業者)自身が新しい加工を展開しています。
食品工学科では、素材への知識を深めるため、「手入れする漁業」「手入れする農業」をカリキュラムに組み入れ、効率とは単に機械化だけでなく、「無駄を省いて(オペレーション)、手間を省かず(マネジメント)」することです。
「手入れ」とはコントロールと違い自然に合わせ試行錯誤しながら、機械化を進め、バランスを崩しやすいシステムに加減を見ながら人の手を加えシステムを強固にして組立て育てる学問です。
素材の育て方から、加工、流通まで、実に100時間を超える授業を行います。
生産(農業・漁業・畜産)→加工→製造→流通→販売とそれぞれの分野で知識と実技を習得して専門士付与の条件としております。
今後、食品工学科が6次産業化における省力化,量産化、新商品の開発などに果す役割は大きいものと考えます。
食品工学の基礎について
食品工学は、宿命的に3つの条件を受け入れなければなりません。
一つは、原料を生物素材とせねばならないこと、
二つ目は、製品を製造する工程が効率的であること、
三つ目は、最終製品が安全で人の嗜好をも満足せねばならないことです。
食品工学全般の基礎知識は極めて膨大であり、Operations-Management-System-Schoolでは、その中でも時代に沿ったニーズのある科目であるHACCPを中心とする専門課程の授業内容です。
どの食品工学にも共通し、企業のニーズに沿った学問が「HACCP」です。
従来、HACCPの基礎知識は製造に従事しながら企業側がトレーニングするものでしたが、現在の食品工場の状況ではHACCPの基礎知識に特別な時間や教育費を設ける余裕がないのが現状です。
HACCP活動は各食品工場の製造工程を完全に把握し、予測できる危害を把握しながら製造活動に携わります。
HACCPは、見た目で区別するのが困難ですが、単なるオペレーションと違うことは、危害要因を予測しながら製造、管理できることです。
HACCPを基礎として、製造を行う者と、HACCPの基礎を知らない者が行う製造とでは、食品の安全性に格差がでます。
「この仕事を、どの頻度で、どの程度行えば、食品安全上問題の無い製品が作れるのか」「この仕事は、どんな理由で実行する必要があるのか」など、書店で販売している参考書を読んでも判らないノウハウが数多くあります。
HACCPを基礎として、製造を行う者は、記録表の把握、クレームへの迅速な対応、意識改革など、顧客に安心を与え、信頼感が高まり、必要な人材として評価されるものと思っております。
食品業界におけるHACCPの必要性は、今後ますます需要が高まるものと思います。
常に動的発展を続けるHACCPは、原材料の受入れから、加工→製造→流通まですべての工程を連携させる「連続HACCPの構築」へと結びつき、食品工場全域のマネージメントシステムとして活躍の領域を広げることになります。
そして、食品工学は、近い将来、人材不足の観点から、ますますその需要は高まり、企業の評価を受けるものと思います。
Operations-Management-System-Schoolでは、食品工学のHACCP を基礎とし、力量ある留学生の人材育成に心掛けていきます。
食品工学科の内容
素材を使い、調理加工から製品まで冷凍・冷蔵・常温とあらゆる食品分野に応用できる管理マニュアルを専門課程を通じて習得します。
ISO22000/HACCP 食品安全マネジメントシステム
海外では日本食人気は高く、新鮮さやヘルシーさといった印象を持たれています。東南アジアでは大手日系外食企業の進出が増えているほか、現地の日本食チェーン店なども増加中です。食品安全マネージメントシステムは習得と学習を繰り返し、着実に運用能力が身についていきます。食品安全マネージメントシステムを2年間に渡り修得すれば、帰国後の就職活動にも効果が得られます。HACCPはアメリカではじまったHazard Analysis Critical Control Pointの略称で危害分析重要管理点のことで、今では世界的に導入が進められています。現在でもアメリカやEU各国ではHACCP認証取得が輸入の条件になっています。東南アジアではHACCP認定施設はまだ少ないのですが、東南アジアのグローバル化が進み、今後拡大していくこととなります。
食品工学科卒業時における資格の付与について
食品工学科卒業時には、以下の資格が付与されます。
・食品工学専門士
食品工学科在学中には、以下の資格が取得可能です。
・食品衛生責任者
・食品安全危害分析製造責任者(予定)
(Food Safety Hazzard Analysis Manufacturing Qualiffied Person)
食品工学プログラムの到達目標
Operations Management System School 実技内容と実技時間 | |||||
区域 | 工程 | 管理基準(管理項目・事項) | OMSSトレーニング時間数 | 記録の 有:無 | 責任者 (リーダー) |
汚染区1 | 原料受入 | 100 | |||
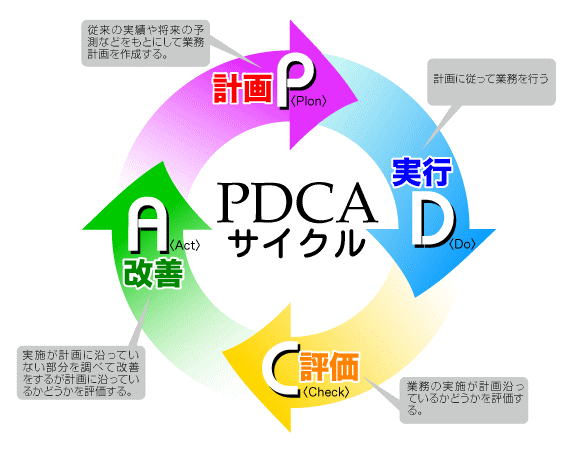
商業実務課程 食品工学科 二年制(書類選考、面接、学力試験等があります)
| |||
科目
| 授業内容
| 1年目
| 2年目
|
専門科目
| 理論
| 150時間
| 150時間
|
実技
| 470時間
| 580時間
| |
一般教養科目
| 習得
| 200時間
| 200時間
|
合計
| 820時間
| 930時間
| |
入学期 4月
学科名 | 修業年限 | 入学定員 | 課程 | 卒業時の称号など |
食品工学科 | 2年 | 20名 | 商業実務専門課程 | 専門士付与 食品衛生責任者 食品安全危害分析製造責任者 *卒業時、資格が付与されます |
一般教養科目
・ビジネスマナー教育
・労働法令教育
・職場体験(インターンシップ)
・語学教育
・ボランティア活動
・地域、社会貢献活動
・コミュニケーション能力育成
・情報リテラシー教育(新聞、インターネット、TV)
・各業界分析
・社会科見学
・読書会、写生、音楽スケジュール
食品工学科 4月入学コース
| 前期(4月8日~8月31日) | |
| 入学式 | 4月 1日 |
| 長期休校 |
4月27日 ~ 5月10日(14日間)
8月 1日 ~ 8月31日(1ヶ月間)
|
| 中・後期(9月1日~3月31日) | |
| 学期始め | 9月 1日 |
| 長期休校 |
12月28日 ~ 1月10日(14日間)
|
| 学位記授与式 | 3月20日頃 / 3月31日頃 |
| 学年終わり | 3月 |
授業料
1、検定料 免除
2,入学金 50,000円(2022年度より)
3、教材費 免除
4、授業料(月額) 35,000円(2022年度より)
*8月の学費は学費サポート制度により免除
学費サポートとは、長期休暇期間の学費は免除し、補習の必要がある場合のみ有料とする制度です。
入学願書応募
文化・教養一般課程 日本語学科
・日本語を学び、日本を学ぶ
「学生の時代に日本の学校で学び、実習体験した経験がある」という外国人が今後増えて、外国人と話すときの共通語として日本語が選ばれることがあるかもしれません。
留学生が日本を学ぶ場合、その目的が「日本語学習」そのものへの興味からというのは、ほとんど考えられません。
単位取得するために学んでいる学生は別として、大多数の学生は日本語の成果を生かして「何か」をすることを期待しているからです。
・日本語の力や学力の個人差に対応した学習と教育
1、対象となる生徒の日本語の力や学習経験。既存知識・学力は多様であり、生徒の個別性に対応した日本語教育を目指します。
2、日本語の力の発達に合わせた学習と教育
生徒の日本語の発達の状況は、一人一人異なると同時にその発達の道筋も多様であり、生徒の日本語の発達を追いながら、その段階に合った学力を行います。
3、一般教養科目としてビジネスマナー・職場体験・ボランティア活動を通じて、日本語の力を高めると同時に必要なコミュニケーション能力や考え方を育成することを目指します。
日本語能力試験については、こちら
入学期 4月
学科名
| 修業年限
| 入学定員
| 備考
|
日本語学科
| 1年
| 40名
| 日本語能力試験受験制度あり
|
文化・教養一般課程 日本語学科 一年制
| ||
日本語
| 習得
| 620時間
|
一般教養科目
| 習得
| 200時間
|
合計
| 820時間
| |
授業料
授業料
1、検定料 免除
2,入学金 50,000円
3、教材費 免除
4、授業料(月額) 30,000円
スケジュール
日本語学科科 4月入学コース
| 前期(4月8日~8月31日) | |
| 入学式 | 4月 1日 |
| 長期休校 |
4月27日 ~ 5月10日(14日間)
8月 1日 ~ 8月31日(1ヶ月間)
|
| 中・後期(9月1日~3月31日) | |
| 学期始め | 9月 1日 |
| 長期休校 |
12月28日 ~ 1月10日(14日間)
|
| 学位記授与式 | 3月20日頃 / 3月31日頃 |
| 学年終わり | 3月 |






